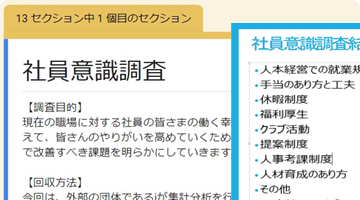第1077号 <検証> 9年間何を実践してヒグチ鋼管は大賞受賞に至ったのか Ⅱ
2025.3.24
道標4)幸せ軸の経営参謀をおく
業績軸から幸せ軸への経営革新は、発想の転換が不可欠になる。このため、正しく幸せ軸の経営を導く知見のある経営参謀をおくことが重要。
それはすでに人本経営の実践に功を成した経営者でもかまわないし、外部の専門家でもよい。
人本経営実践の最高峰にある伊那食品工業を創りあげた塚越寛さんは「いい会社をつくりましょう」(文屋)など数冊、ご自身の経営哲学と実践例をご高書にまとめられています。それを常に脇におき経営判断の指針にしていくことでも十二分に有力な参謀となります。外部の専門家を選択する場合、間違っても「ジョブ型雇用」を推奨するような業績軸のコンサルタントやシンクタンクを招いたり、影響を受けてはいけません。幸いにも樋口社長は拙著「人本経営」を読了していただき、当方を経営参謀として迎い入れてくださいました。「未だに小林先生の他に経営に関して指導を仰ぎたい人は出てきていません。」と有難いお言葉をいただき感謝の念で溢れます。
道標5)人本経営を学ぶ
まず経営者がしっかりと人本経営を学ぶ。そして、どんなことをしていけばよいか明確に腹落ちさせていく。次いで右腕、左腕、そして次世代リーダー、さらには全社員へと学びの場を増やし人本経営を浸透させていく。
幸せ軸経営実践の重要性を悟った樋口社長は2016年「人本経営実践講座」大阪2期生として、右腕幹部の小川さんと参加し人本経営とは何たるか、しっかり確実に学んでいかれました。そして、以後10期まで毎期、数名の社員が参加し総勢24名が受講し修了生となっています。熱心に人本経営のあり方をヒグチ鋼管さんなりに試行錯誤しながら実践していかれました。
道標6)人本経営を実践する
人本経営の学びを自社に展開していく。ここは選択肢がある。
経営者自らが陣頭指揮をとっていくことが一つ、
もう一つは、外部の専門家に頼り社風をよくするサポートを委ねる方法。
なぜ選択肢がふたつになるかというと、経営者のなかには、「幸せ軸」の人本経営を学び、自らが組織風土を変えていくことができる方もおられますが、「業績軸」の経営感覚が染みつき、自ら率いていくことに難しさを感じる方もいるからです。ヒグチ鋼管は、明確に前者でした。そして前述のように毎期、幹部や次世代リーダーを人本経営実践講座に送り出していたので、職場に人を大切にする経営に対する共感、共鳴の輪が年々拡がっていき盤石な幸せ軸の企業文化が形成されていきました。
道標7)求人募集広告で「幸せ軸」を強く打ち出す
ここまでのステップを踏んできたら、次は、採用。堂々と求人広告に、今、わが社は社員が幸せになる人本経営に取り組んでいて、やりがい、働きがいのある企業風土づくりをいちばん大切にしていると打ち出すことができる。
まだ風土改革が実現出来ていなくとも、幸せ軸経営を志向しているという求人広告でのメッセージは、必ず一定数の求職者に響くとの助言をヒグチ鋼管では素直に受け入れ展開されました。その結果、前号で紹介したとおり10人もの採用をあっという間に実現したのです。今やこの時採用した人材は中核となってヒグチ鋼管の屋台骨を支え今日に至っています。ヒグチ鋼管の人本経営の実践は極めて模倣しやすい事例であり再現性は保証します。後はやるかやらないか、これに尽きます。
このコンテンツの著作権は、株式会社シェアードバリュー・コーポレーション(以下SVC)に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、SVCの許諾が必要です。SVCの許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。