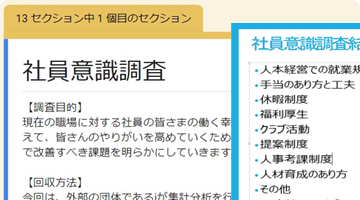第1081号 人的資本経営とジョブ型を紐づけたのが最大のミステイクだった
2025.4.21
引き続き、政府推奨のジョブ型人事指針(以下「指針」)で推奨された企業の実態解明を続けていましょう。指針で1番目に紹介されている会社が富士通です。
富士通、早期希望退職を募集 費用200億円計上も人数は非公表~2024.10.31朝日新聞
富士通は31日、国内の間接部門の幹部社員を対象に、早期希望退職を募ったと明らかにした。募集人数は公表していない。すでに募集を締め切り、応募者の多くが10月末で退職したという。退職金の積み増しなどの関連費用として200億円を同日発表した2024年9月中間決算に計上した。~以上引用
かつて成果主義導入で大失敗した富士通。その反省を踏まえたということですが、ジョブ型雇用には熱心に取り組んできています。2020年、ジョブ型を導入しています。その後、2022年、50代以上の幹部社員約3千人を希望退職させています。そして、今度は間接部門のリストラです。人数非公表となっていますが、22年の3000人リストラの際には650億円の費用をかけたと報じられていますので、その3分の1となる1000人規模のリストラになったものと考えられます。業績が停滞しているからリストラを繰り返していることは明白です。→ 富士通業績
この会社、わが社はSDGsに貢献すると大々的にサイトで公表していますが笑止です。自社の社員の雇用も守れないで誰一人取り残さないSDGsに貢献とよく言えるものであると開いた口が塞がりません。
こういう経緯をたどっている会社のジョブ型人事をあえて政府は典型例としてジョブ型人事指針に掲載しているのです。しかも1番目に。これは悪意を感じざるを得ません。
ジョブ型雇用は持続可能性を高めていない
ここまで指針で事例紹介された20社のうち4分の1にあたる5社の現在を紹介してきました。いずれもジョブ型雇用、人事制度を導入したものの業績は低迷し大量リストラをしています。ほかの企業の事例も今後、追っていきますが、似たようなケースが出てくる可能性は濃厚です。つまり、ジョブ型雇用は企業の持続可能性を高めることに貢献できていないということが明らかです。業績という「結果の質」に大きく影響を与える組織人事でいちばん大切にしなければならない会社と現場の社員の「関係の質」をいとも簡単に破壊してしまう装置がジョブ型の正体であると言わざるをえません。
先進的な識者は、米国はすでにジョブ型にベクトルは向いていないと指摘しています。
ジョブ型人事制度は時代遅れ?アメリカで本当に注目されている働き方を解説!
実は米国は、ジョブ型ではなく、従業員の幸せや組織への帰属意識、エンゲージメントなどに着目している。アメリカの企業はジョブ型にベクトルが向いていない。むしろアメリカはジョブ型人事制度にとらわれず、新たな雇用形態を追求している。~以上引用
グローバル、グローバルという金科玉条の掛け声で米国追随だとジョブ型と叫んできたものの、とっくに周回遅れになっているというのが現実ということなのでしょう。
実際、人的資本経営の国際規格とされたISO30414を検証すると定められた58指標にジョブ型を重視しているかどうかといった視座は全くありません。それどころか「内部登用率」とかあえて後継者計画という項目を一つ設けて「内部承継率」「後継者候補準備率」「後継者の継承準備度(即時)」「後継者の継承準備度(1-3年)(4-5年)」とむしろメンバーシップを重視した指標を1割も盛り込んでいるのです。そもそも人的資本経営とジョブ型は別物であるということがここからもわかります。
人的資本経営の実践手法としてジョブ型を紐づけたのは、ご紹介した「人材版伊藤レポート」です。各方面に多大な影響を与えている一橋大の伊藤邦雄教授ですが、残念ながら、この紐づけはミスリードをしてしまったと言わざるをえません。ジョブ型が正解ではなかったと学者の矜持として今からでも訂正をしてほしいものです。今なお好業績、抜群の雇用安定を誇る伊那食品工業を筆頭とする幸せ軸経営の会社群はひとつとしてジョブ型の企業は存在していません。それが正答で真実なのです。
このコンテンツの著作権は、株式会社シェアードバリュー・コーポレーション(以下SVC)に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、SVCの許諾が必要です。SVCの許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。